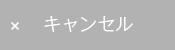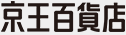お中元とは?お歳暮との違いや相場価格・押さえておきたい注意点
お中元は、日頃お世話になっている方への感謝の気持ちを伝える、日本ならではの贈り物の習慣です。毎年夏になると、上司や親戚、取引先などに品物を贈る機会が増えますが、「いつ贈ればいいの?」「何を選べば失礼にならない?」と迷う方も多いのではないでしょうか。
当記事では、お中元の基本的な意味からお歳暮との違い、贈る時期の地域差、相場価格、選び方のポイント、さらにはのし紙のマナーまで、初心者にも分かりやすく解説します。
1.お中元とは?お歳暮との違い
お中元とは、主に7月からお盆の期間にかけて、お世話になっている人に贈り物をする風習を指します。感謝の気持ちに加え、相手の健康を願う気持ちも込めて、会社の上司や遠方の家族などに贈り物をすることが一般的です。
お中元の起源は中国に関係があります。中国の暦の上では、1月15日が「上元」、7月15日が「中元」、10月15日が「下元」と分けられています。そして、中国では7月15日が祖先を供養する日となり、その風習が日本の仏教の風習と混ざったことで、お中元は「感謝の気持ちを伝える習慣」となりました。
お歳暮もお中元と同様に、お世話になった人に対して感謝の気持ちを示すために贈ります。しかし、お歳暮は1年の締めくくりとして贈るため、お中元とは贈る時期が異なっています。
1-1.お中元の相場価格
お中元の一般的な相場は、3,000~5,000円です。決まったルールはないものの、身内の人に贈る場合は3,000円、会社の上司など目上の人に贈る場合は5,000円といったケースが見られます。
そのほか、贈る相手別の相場は以下の通りです。
| 取引先 |
会社の上司に贈る場合と同様に、5,000円程度が望ましいとされています。お得意様に贈る際は、10,000円を限度に選ぶこともあります。 |
| 習い事の先生 |
習い事の先生へのお中元は、現在では贈らないケースも増えています。先生がお中元の受け取りを拒否していたり、お中元を贈る習慣がなかったりするところでは、必ずしもお中元を贈る必要はないと言えるでしょう。 |
お中元を贈る場合は、3,000~5,000円程度が多い傾向です。
2.【地域別】お中元を贈る時期はいつ?
お中元の贈る時期は、地域によって異なります。ここでは、地域別に適したお中元の時期と注意点を解説します。お中元を贈る際は、相手の地域に合わせた心遣いを大切にしましょう。
2-1.北海道
北海道ではお中元を贈る時期は「7月15日~8月15日」が一般的です。旧盆の時期に合わせた慣習によるものですが、近年では関東など他地域の影響を受け、7月上旬から贈るケースも増えてきました。
北海道は本州からの配送に時間がかかるため、余裕を持ってお中元を手配しましょう。迷った場合は、全国的な基準でもある「7月15日頃」に届くようにすると無難です。
2-2.東北
東北地方(青森・岩手・宮城・秋田・山形・福島)では、「7月1日~7月15日」がお中元の正式な時期とされています。この期間は他の地域に比べて早く、かつ短いため、早めの準備が必要です。
この時期は配送が集中することで日時指定が難しくなるケースもあるので、6月中に発送するのが安心です。
2-3.関東
関東地方(茨城・栃木・群馬・埼玉・千葉・東京・神奈川・山梨)も、東北と同様に「7月1日~7月15日」がお中元の時期です。この背景には明治時代の改暦で新暦を採用したことがあり、全国でも比較的早いタイミングが一般的となりました。
期間が短いため、配送の集中を避けるには6月後半からの手配がおすすめです。
2-4.北陸・甲信越
北陸・甲信越(新潟・富山・石川・福井・長野)は地域内でも時期が異なります。新潟県や石川県金沢市では「7月1日~7月15日」が主流ですが、富山県や石川県能登町などでは「7月15日~8月15日」に贈る傾向があります。このため、どちらの時期か判断に迷った場合には「7月15日を目安」に届くようにするのが無難です。
地域差があることを理解し、贈る相手の所在地に応じて調整しましょう。
2-5.近畿
近畿地方(大阪・京都・兵庫・滋賀・奈良・和歌山)では「7月15日~8月15日」が一般的なお中元の時期です。最近では、関東の影響で時期が前倒しになる傾向も見られますが、明治の改暦で旧暦に準じた日程が継続されていることが背景にあるので、基本的には旧盆までに届くよう贈りましょう。東海地方も、近畿地方と同様の時期に贈るのが風習となっています。
2-6.中国・四国
中国・四国地方(鳥取・島根・岡山・広島・山口・徳島・香川・愛媛・高知)も、「7月15日~8月15日」が主なお中元の時期です。この期間を過ぎると「残暑見舞い」として扱われます。暑さが厳しい地域のため、9月上旬までは残暑見舞いとして贈ることも許容されています。
2-7.九州
九州地方(福岡・佐賀・長崎・熊本・大分・宮崎・鹿児島)は全国でも最も遅い「8月1日~8月15日」が基本のお中元時期です。お盆の時期に合わせた慣習ですが、お盆休みによる配送の混雑を考慮に入れ、7月中に贈る動きも増えています。特に都市部では前倒しされる傾向にあるため、相手のスケジュールに配慮して手配しましょう。
2-8.沖縄
沖縄県ではお中元を贈る時期が旧暦のお盆「7月13日~15日」に合わせられます。この期間は「ウンケー(13日)」「ナカビ(14日)」「ウークイ(15日)」と呼ばれ、祖先を迎え、もてなし、見送る重要な行事が行われます。そのため、お中元は旧盆に間に合うよう早めに贈るのが慣習です。日付が年ごとに変わるので、旧暦を確認して贈りましょう。
3.お中元の選び方
お中元は日頃お世話になっている方へ感謝の気持ちを伝える贈り物です。そのため、贈る際は相手の好みを考慮するとよいでしょう。ここでは、お中元の選び方を解説します。
3-1.好みが分からなければ定番ギフトがおすすめ
相手の好みが分からない場合には、定番のお中元ギフトを選ぶのがおすすめです。夏の贈り物として人気が高いのは、そうめんやゼリー、水ようかんなどの涼を感じられる食品です。また、日持ちがする乾麺やお茶・コーヒー、調味料なども重宝されます。
子どもがいる家庭ならジュースの詰め合わせ、年配の方には体にやさしい食品など、相手のライフスタイルに合った定番品を選ぶのもよいでしょう。洗剤やタオルといった日用品も喜ばれる定番ギフトの1つです。
3-2.お中元で贈ってはいけない品物もある
一方で、お中元では、避けた方がよい品物もあります。たとえば刃物は「縁を切る」という意味を連想させるため不適切です。また、現金や商品券は「金品を施す」と受け取られることがあり、特に目上の方には失礼とされます。親しい間柄でも、贈る相手によっては誤解を招く可能性があるため、贈る品には慎重な配慮が必要です。
4.お中元にのしをつけるときのマナー
お中元には、贈る品物だけでなく、のし紙(掛け紙)にも気配りが求められます。のし紙の種類や書き方、掛け方などに注意を払うことで、より丁寧で失礼のない贈り物となります。特に目上の方やビジネス相手に贈る場合は、マナーを正しく理解しておきましょう。
4-1.のし紙の選び方
お中元ののし紙には、「紅白の蝶結び」の水引が印刷されたものを選ぶのが一般的です。蝶結びは「何度繰り返してもよいお祝いごと」に用いられる水引で、継続的なお付き合いを願うお中元にふさわしいとされています。
また、「短冊のし」と呼ばれる簡易タイプも近年増えており、簡易包装の需要に合わせて選ばれることもあります。どちらを選んでもマナー違反にはなりませんが、フォーマルな場面では従来の掛け紙を選ぶとより丁寧な印象を与えられます。
4-2.表書き・名入れの書き方
のし紙には「表書き」と「名前」を記載します。表書きは水引の上部中央に「お中元」または「御中元」と書きます。お中元の時期を過ぎてしまった場合は、「暑中御伺」または「残暑御伺」と表記を変えるのがマナーです。
名前は水引の下に記載し、基本的にはフルネームで書きます。夫婦で贈る場合は夫の名前を中心に、連名の場合は3名までを右から順に記入、4名以上の場合は代表者名と「他一同」とします。会社名を添える場合は、個人名の上に小さく記載しましょう。
4-3.のし紙のかけ方
のし紙のかけ方には「内のし」と「外のし」があります。内のしは品物にのし紙をかけ、その上から包装する方法で、控えめな印象を与えます。宅配便で贈る場合は、配送中にのしが汚れるのを防ぐため、内のしが選ばれることが一般的です。
一方、外のしは包装の上からのし紙をかける方法で、贈り物の意図がすぐに伝わるため、手渡しに適しています。贈る状況や相手との関係性を考慮して、適切なのしの掛け方を選びましょう。
2025年京王のお中元特集